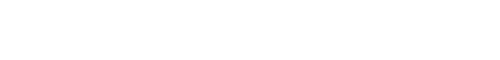当サイトでは、一般的なキャッシュフロー計算書とは考え方がかなり異なるキャッシュフロー計算書を紹介しています。なぜなら、一般的な定義では不可能な処理があり、より実務に即したキャッシュフロー計算書が必要だと考えたからです。
一般的なキャッシュフロー計算書とは
一般にキャッシュフロー計算書は、一会計期間における現金等(現金及び現金同等物)の範囲を決め、その流入及び流出、つまり収入と支出(キャッシュフロー)を、一定の活動区分別に表示する財務諸表とされています。
金融庁の企業会計審議会が公表した「(連結)キャッシュフロー計算書等の作成基準(以下「作成基準」と略)」では「キャッシュフロー計算書とは一会計期間におけるキャッシュフローの状況を一定の活動区分別に表示するもの」と定義しています。実務上は作成基準を具体化した「(連結)財務諸表等におけるキャッシュフロー計算書の作成に関する実務指針(以下「実務指針」と略)」によって作成します。
「実務指針」5では「キャッシュフローとは、現金等の増加又は減少を意味する。したがって、現金等の増加又は減少を伴わない交換取引等はキャッシュフロー計算書には反映されない」としています。
また、同24(非資金取引)では「非資金取引の内容によっては、部分的にキャッシュフローを伴う取引もあるが、その場合にはキャッシュフローを伴う部分についてのみキャッシュフロー計算書で報告しなければならない」としています。
さらに同41(相殺取引)では「相殺取引はキャッシュフローを伴わないため、キャッシュフロー計算書における報告対象とはならない」と定めています。
これらから明らかなように、作成基準や実務指針(以下「作成基準等」という)では、相殺等の非資金取引はキャッシュフローを伴わないことから、キャッシュフロー計算書の対象としないこととしています。つまりキャッシュフロー計算書の対象を、決済手段としての資金に限定しているのです。
一般的なキャッシュフロー計算書は実務に即していない
一般的な定義では、現金等の範囲を決め、その収入及び支出を分析します。借方や貸方に現れる現金等が、何に由来するものなのかを分析してキャッシュフロー計算書をつくるのです。そのようなキャッシュフロー計算書を、ここでは便宜的に「分析型」と呼ぶことにします。
実はこのような分析型のキャッシュフロー計算書は実際的でない面があります。例えば、給料と併せて通勤交通費を支給する際に、従業員貸付金の返済を天引きする場合です。このようなことは、多くの会社で行われているのではないでしょうか。
この場合の仕訳を示すと、以下のようになります(源泉税の控除等を入れると複雑になるので、ここでは省略してあります)。
作成基準等に沿って処理をすると、支給額950がキャッシュフローということになります。しかしキャッシュフロー計算書へは、これをどのように表示するかが不明です。950を「給料1,000」と「交通費50」に按分してキャッシュフローがあったとするのでしょうか? しかしこのような場合は、「給料1,000」と「交通費50」の決済、そして「貸付金100」の返済があったと考えるのが自然ですね。
このように、作成基準等は理論的にはともかく、実際的ではない面があることがお分かりいただけると思います。
実務面からみると現預金以外の決済手段も含めるべき
実務面からみると、現金や預金といった限られた決済手段だけでなく、他の決済手段も含めた取引がキャッシュフロー計算書に反映されるべきであると考えるべきではないでしょうか。
このようなことから私は、「相殺等の一切の決済手段による取引も含めて、キャッシュフロー計算書に表示すべきである」という結論に至りました。つまりキャッシュフロー計算書の本質は、決済を表すものであると考えるようになったのです。
その場合、取引がキャッシュフロー計算書に表示するかどうかは、決済が行われたか否かによることになります。分析型に対して、決済という行為をキャッシュフロー計算書に表示すべきと考えますので、このような考えのキャッシュフロー計算書を、ここでは便宜的に「決済型」と呼ぶことにします。
どうして相殺等も含めた決済を対象としたほうが良いのでしょうか。その根拠は3つ考えられます。
第1は、すでに述べたように、現金等の増加及び減少に限定した場合、その増減が何なのかが説明できない場合があることです。
第2は、実務上では決済の表示で行われていることです。
例えば営業収入の金額を求めるには、売上に売上債権の増減を加減して求めることとされています。
[実務指針Ⅲ6.(1)仕訳] 一部省略
この仕訳には相殺を除外しておらず、その内容は決済を表しているものと思われます。
第3は、現金等の増加、減少を検証する構造になっていないことです。現金等の増加、減少ではなく、現金等の増減差額を検証する構造になっています。
分析型では不可能だが決済型では可能な例
分析型では説明できない取引が、決済型では可能であることを、もう少し例を挙げてみていくことにします。
以下では、財務会計とキャッシュフロー会計の両方の処理を示します。キャッシュフロー会計は更に、分析型と決済型に分けて検討します。少し面倒ですが、辛抱して読んでください。
①A社への売掛金200を現金で回収した。
イ.財務会計の処理
ロ.キャッシュフロー会計の処理
ⅰ分析型
ⅱ決済型
分析型と同じ
この取引は、分析型も決済型も同じ仕訳になります。
②A社への売掛金200を、一部は仕入れ代金100と相殺し、残額100を現金で回収した。
イ.財務会計の処理
ロ.キャッシュフロー会計の処理
ⅰ分析型(現金の100だけを仕訳の対象とする)
ⅱ決済型
この取引は、売掛金の回収という1つの決済に、現金と買掛金の2つの決済手段を用いています。分析型では現金で決済した部分のみを対象とし、決済型では現金及び相殺の両方を対象としています。このように範囲が異なるものの、分析型でも処理可能です。
③A社に売掛金200とともに、営業保証金1000を差入れてもらい現金で回収した。
イ.財務会計の処理
ロ.キャッシュフロー会計
ⅰ分析型
ⅱ決済型
分析型と同じ
この取引は、2つの取引の決済に現金のみを決済手段として用いています。したがって分析型でも同じ処理になります。
④A社とは商取引契約を解除して債権・債務を清算し残額を現金で決済した。
契約解除時の債権・債務の状況
売掛金 500;買掛金 200;預り保証金1000
イ.財務会計の処理
ロ.キャッシュフロー会計
ⅰ分析型
分析型では上記の現金700の内容は説明できません。
清算時には債務が多く、それを一部は売掛債権と相殺し残額を現金で決済しているため、現金の部分だけを取出し、どの部分かを説明することはできません。
ⅱ決済型
決済型では、決済がされたか否かでキャッシュフローの対象とするかどうかが決まります。これらの取引は精算のために「決済」した取引ですから、キャッシュフローの処理が可能です。
このように検討すると、分析型で処理できる取引は、①②③のように、現金に対応する決済の部分が一意に説明できる取引です。
①は売掛金の決済に、1つの決済手段である現金が対応していますから当然説明できます。
②は売掛金の決済に、現金と買掛債務の2つの決済手段が用いられています。そのうち現金による決済の部分も売掛金の決済ですから説明できます。
③は2つの取引の決済に、1つの決済手段である現金が用いられています。従って原因である商取引ごとに現金を配分することで処理できます。
④は2つの債務を決済するために現金と債権による相殺の2つの決済手段が用いられています。現金の金額は3つの債権・債務の差額です。そのために2つの債務のいずれも、個別には現金または債権は対応していません。
こうなると決済手段の1つである現金のみを取出して、いずれの商取引に対する決済かを決めることはできません。
このように、分析型では取引のすべてが説明できるとは限りません。分析型ではキャッシュフロー計算書に表現できない取引が存在する可能性があるのです。
そのため分析型では、直接法によるキャッシュフロー計算書を作成する場合、実務では行き詰まってしてしまいます。そのような場合には、決済型を使うしか方法がありません。私の提唱している決済型の表示方法は、理論的かつ実務的であると言えます。
分析型では現金等の増減に着目してキャッシュフロー計算書を作成することから、分析が可能でなければなりません。しかし決済型では現金等による決済手段に限定しないため、全ての仕訳を集計した試算表からでもキャッシュフロー計算書は作成可能となります(試算表からキャッシュフロー計算書を作成する原理については「CFSの作成原理」のページをご覧ください)。